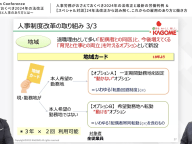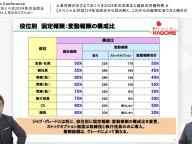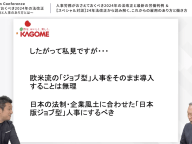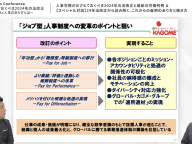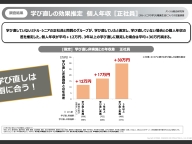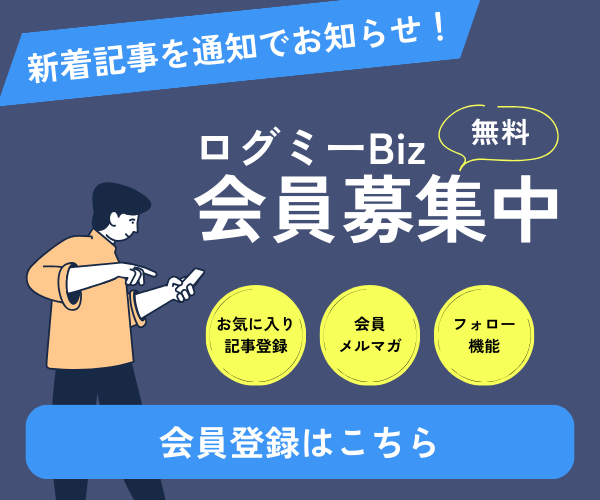家事代行サービス「ベアーズ」を創業するまで
藤岡清高氏(以下、藤岡):日本における家事代行のパイオニア、「ベアーズ」の創業経営者、そして2児の母としてイキイキとキラキラと輝いているゆきさんですが、そんなゆきさんの生い立ちについて教えてください。
高橋ゆき氏(以下、高橋):私は、写真家の父と起業家の母の間に生まれました。小さいころは母の強い思い込みにより、お腹の中にいるころから男の子だと思って出産を迎えたらしいです。
ですから、生まれてから本当に男の子みたいな恰好をして育てられて、私のこの男勝りっぽい中身はそういう生い立ちから始まっていると思います。小さなときからすごくはっきりしてる子でした。「白か黒かはっきりしてよ」という感じですね。
起業家の母は常にアグレッシブで、エネルギッシュで太陽みたいな人で、写真家の父は非常に芸術肌で月のような人でした。
家の中に常にこの神秘的であり発想力があってクリエイティビティあふれる父と、ダイナミックで、パワフルでエナジー150パーセントみたいな母の間に育ちましたので、とにかく小さなころから人生って素敵だなと思う、超スーパーポジティブガールだったわけです。
小学校6年間はずっと学級委員長とか代表委員とか、だいたい「長」を任されることが多くて……。それで、自我が出てくるような年になると、周りが非行に走る子もいたり、いじめられたりいじめたり、もしくは派閥みたいなものがあったり、1人で逆にいじけてる子がいたり、とにかく正義感の塊で、「それをなんとかしないと!」と思っていました。
どんな子も「ほっとけない」みたいな感じです(笑)。誰に頼まれたわけじゃないんですど。でもそうやって正義感を奮わせてるわりには、実は超デリケートで、哲学を勉強する少女で、ゲーテの詩集を読んだりしていました。
中1のころから胃が痛いとか言い始めて、中2のころには胃カメラの常連客になっていました。なぜ宇宙は生まれたのかとか、なぜ人はここにいるんだとか、そこまで考え込んでしまう、とてもデリケートな子だったみたいです。
そんな私にとって父は人生の辞書みたいな人でした。なんでも父に聞けば物事の考え方や自分の心の落ち着け方が(わかって)、私のメンターであり師匠みたいな感じで、お父さん子でした。
そんな父にいつも「なんで人は人をいじめるの?」とか「なんで人はこうすると悲しむの?」とか「なんで人はこうすると喜ぶの?」などを何でも聞いていて。女の子として月経が始まったら、体のメカニズムさえうちの父が図解してくれて教えてくれました。
父親から教わった人生観
ある日、私がデリケートな16歳ぐらいのときに父に突然呼ばれて、「ゆき、ちょっと落ち着け」と。「世の中そんなに心配したり悩んだり不安に思うことは不要なんだ」と。「明日の太陽は誰にでも上がってくるから、そんなことよりも今を一生懸命生きて、明日の朝日をありがとうの気持ちで迎えることのほうがよっぽど人生が美しく輝くよ」ということを父が教えてくれました。
本当に人生にとってとんでもなく悲しいとか、とんでもなく大変なことというのは、自分の大切な家族や親とか子供とか恋人などが怪我をしてしまうとか、大病する、最悪亡くなってしまう、こういうことが大変なことであって、それ以外は大変なことなんてないんだということをバシッと言われました。師匠でありメンターでありコーチみたいな父はそう力強く教えてくれました。
藤岡:“高橋ゆき”の原型としての価値観は16歳のときにほぼできたということですね。
高橋:そうです。すごくデリケートすぎて中2から毎年胃カメラを飲んでいたような、些細なことでも傷つきやすい子だったので。
だからこそそのタイミングで父はこういう話をしてくれたと思うんです。周りの大事な人たちが悩んでいたり、悲しんでいたりするのを考えると、いてもたってもいられず自分のことのように心配していました。
藤岡:ゆきさんは感受性が強すぎたんでしょうね。
高橋:そうですね。きっと父は、勝手に傷ついたり悲しんだりしてる私の姿を見て、うちの娘はこんなことをずっと続けてたら心身が持たないと思って言ってくれたのかもしれません。
「もっと自分を大事にすることが本当の意味でお友達やゆきが心配している人たちを守ったり導くことにつながるんだよ」と。「だから自分のことを大事にするために、胃カメラばっかり飲むような考え方じゃいけないよ」と教えてくれたのです。その教えがあって今の私があるのかなと思います。
母の会社の倒産、26歳で無一文に
藤岡:ゆきさんのお母様についても教えていただけますか?
高橋:母は25歳まで、とある商社の普通のOLで役員秘書をやっていたんですね。それこそお茶を出したり応接室にお通ししたり。
ところがうちの母も当時にはめずらしいパワフルな女性でしたから、突然「あたし起業する」と言って周囲を驚かせたみたいです。当時は女性が「起業」するなんてあまり考えられなかった時代でしたから。
女性が起業というのはとんでもなくレアケースで、母の親戚はみんなびっくりして、「女が1人で会社を興すのなんてやめときなさい」と諭したらしいんです。でもうちの母は言い出したら聞かないので、自分の親をはじめ、叔父とか叔母からお金を集めて、借りて、出版社を立ち上げるんですよ。
いきなり25歳で脱サラをして、今でいう起業家、アントレプレナーとなり、それで彼女は丸々25年間経営するんですね。
大人になって社会を見はじめた私は、母のことを反面教師で嫌いな部分があって、「経営者としてどうなのそのやり方?」「そんなことじゃ社員がみんな離れていってしまうよ」みたいに思っていたんですけど、結局倒産してしまったんです。
私が生まれたときにはもう母の会社があったから、まさか自分の生まれ育っていく過程で親の会社が倒産する日が来るなんて思いもしなかったんですが、私が26歳のときに倒産してしまったんです。
倒産の後始末とか処理を全部私がやりました。でも実は倒産をした経験こそが今の私の経営者としての、お金では買えないものすごい経験になりました。
倒産後の処理をするために、弁護士事務所で半年間、弁護士の補佐員として働きました。弁護士さんは債権者とか債務の問題とか関係性がわからないから、役員でなかった誰か1人だけを雇う必要があって私が担当しました。その経験が母親が残してくれた最高の贈り物だったと感謝しています。
藤岡:ふつう26歳では経験しないことを予期せず経験するわけですが、お母様の倒産はゆきさんにどのような影響を及ぼしたのでしょうか?
高橋:どうやって会社はなくなっていくのか、どうやって会社は処理されるのか、どうやって立ち直していけるのかというのを全部見ることができました。
また弁護士事務所にいると、自分の事案以外に起こるいろいろな事件を間近で見れたことも新鮮で勉強になりました。
自分が今まで何不自由なく暮らしてきたところが、突然一文無しになって親を面倒見なきゃいけない立場になっってしまうし、社会人になってから、初任給からずっとコツコツ貯めてきた本当になけなしのお金が、全部家族のために渡してなくなってしまうし。
音を立てて自分の20何年間の人生がフルリニューアルされていく、音が変わって、さらにテレビのハイビジョンの宣伝じゃないけど全部の色が変わっていくみたいな感じですね。26歳でそういう経験をしました。
それで、倒産・破産とはこういうことなんだと。今度はじゃあ、うちの父と母が貧乏になって、不幸かと言ったらぜんぜん不幸じゃなくて、志と心が美しければ破産なんていうことも怖くはないんだなということもそこで学んだし、もっと大事なものもあるということも気づかせてもらいました。
破産後の人間関係の変化
藤岡:破産後、日々の生活や人間関係はどうなりましたか?
高橋:変わりましたよ。極端に言うと、10分の8ぐらいの人が親の元から離れていってしまった。友達と思っていた人も含めて、10人中8人くらいは離れていってしまいました。
経営者のみんなに言いたいのは、自分に対してみんなが「すごいですね」とかチヤホヤしているのではないということ。自分の持っている会社の大きさに「すごいですね」などと言われているだけなのです。そこで人は勘違いしてしまうんですよね。ですから、そうじゃないということを常に思って謙虚でいないといけません。
つい1日前まで「お宅はすごいですね」と言ってた人が、破産の通知が流れた瞬間に手のひら返したみたいに「だと思ったわよ」みたいになってしまう。「昨日までと態度が違う」そのようなことがたくさん起きました。
(それは)辛い経験でしたけど、良かったと思います。その原体験が今の私の経営者思想観を本当に固めてくれました。
もしかしたら、26歳のときが一番人生のどん底かもしれません。ストレスとかショックでまつ毛は抜け落ちてしまうし、手の皮膚が朝起きたらクロコダイルみたいになっていて……。そんな状況で、1日で使えるのは500円だけでした。
そのときはもう結婚していたのですが、よく移動販売で来ていたお魚屋さんは、そういう私たち夫婦の状況を察してくれて、「ゆきちゃんは明るいから、ちょっと待ってなさい」と。意味がわからなかったのだけど、近所の方たちがお店からいなくなるとそっと余ったお魚とかをくださったんです。「お金は要らないから」「鶴の恩返しでいいよ」と言っていただいて、人の優しさに心が震えました。
お肉屋さんは、いつも一番安いお肉しか買えなかったのでそれも察してくれて、帰り道に「今日はなんか重いな」と思うと、メンチカツやコロッケがおまけで入っていたこともありました。
週のほとんどをそのお魚屋さん、お肉屋さんに助けてもらっていました。ベアーズを創業して5、6年目のとき、そのお魚屋さんとお肉屋さんにお礼を言いに行きました。そのときは、これまでのお礼も込めてたくさんのお魚とお肉を買わせていただきました(笑)。
藤岡:倍返しどころじゃないですね(笑)。
高橋:そうですね。でもそんなふうに、なんでも周りに助けられて私たちは生きているのだと思います。自分よがりの人生ではダメで、自分の生活体験の原体験がすべての源にある。志やあきらめない心の源になるのはそういう原体験だと思います。
留学志望から一転、営業ウーマンに
藤岡:少し翻って、ゆきさんのお母様が倒産される前までの、学生時代からOL時代のお話も教えてもらえますか?
高橋:高校3年生ぐらいに戻りますね。卒業後は海外での生活を希望していて、父と母に「外国の大学を受けたい」と言ったら、やっぱり驚かれました。
「カナダの大学に行くから」と言ったら父が、「1人娘がいきなり海外に行くのは嫌だ、とりあえず短大に行ってくれ」「短大に行って、20歳で卒業したらそこから2年間はカナダに行きなさい。そうすれば日本の4大を卒業した人と同じ年で卒業できるから」と言われて、短大の英文科に行きました。
そのとおりに短大を卒業するころには、カナダ行きも決まっていました。ところが、祖母が脳梗塞で倒れてしまったんです。カナダ行き目前の19歳のときでした。
祖母を看病・介抱していて、「私、カナダに行ってる場合じゃないな」と思っていたんですけど、祖母を看病してる母までが倒れてしまって、母も祖母と同じ病院に入院してしまったんです。
それを見たときに私は、「これはもう神様が『カナダに行くのは今じゃない』と言っているのだな」と思いましたが、卒業が再来月に迫った1月の出来事だったので、その時点で当然就職も決まっていませんでした。
カナダ行きは取りやめようと父に相談しました。父も納得してくれましたが、就職先も心配してくれて、「じゃあお前、就職どうする」と言われたときに、部屋にある前年の9月号の就職ジャーナルという雑誌が目に入りました。
もう年が明けて1月だというのに、その9月号をめくって見たら、IT企業で社員の似顔絵がたくさんあるとてもおもしろい広告を使ってる会社があって、「この会社しかない」と思い、この1社だけに履歴書を送りました。
すぐに先方の市ヶ谷にある会社から電話がかかってきて、「面接に来てください」と。「来年ですよね、年度を間違えてますよね」と言われたから、「いえ今年から、再来月卒業で、4月入社で大丈夫ですか」と言ったら驚かれて、「何かあったんですか? こんな時期に就職活動してて」という感じでした(笑)。
「実はこういう事情で母が倒れて、祖母も倒れて……」とお話ししたら、「そういう事情があるならば特別に面接します」と言っていただいて、市ヶ谷に行ったらある男性が面接してくれて、「あなたは事務の仕事は大丈夫そうですか?」と聞いてきたんですけど、「事務じゃなくて営業をさせてほしい」と。新卒で営業未経験なのにそう言ったら、そこでも驚かれました。
それでその男性が「ちょっとここに座って待っててね」と言って部屋から出ていったら、その部屋の向こうで誰かに電話してるわけですよ。
しばらくして戻ってきて、特別に社長が会ってくれるということで本社まで行くように言われたのですが、そのときに本社が札幌にあると知りました。
それで札幌まで飛び、社長面接を受けさせていただき、社長に「君は事務ではなく、営業をやりたいと言っているようだが、本当にやれるのか?」と聞かれましたので、「社長らしくないですね。やらせてもいない人間に『やれるのか?』と聞きますか?」と切り返してみました。
そしたら、「そうか、気に入った!」「うちの会社始まって以来の営業ウーマンだから期待するよ」と言っていただいて、初めて営業マンになったのです。それが20歳のころです。